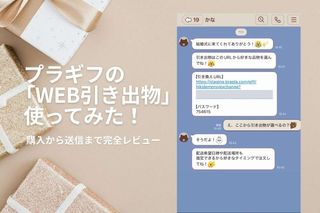結婚式招待状の切手はこれで安心!切手の選び方&貼り方ガイド

結婚式の招待状を出すときは、切手を貼る必要があります。
結婚式の招待状に使える切手にはさまざまな種類があり、選び方や貼り方などの基本情報は知っておきたいところです。
- この記事はこんな人にオススメ!
-
- 結婚式の招待状を出したい
- 結婚式の招待状に使える切手が知りたい
- 切手の選び方や貼り方が知りたい
今回はこのような方に向けて、結婚式の招待状に必要な、切手の選び方や貼り方を解説します。
結婚式の招待状に使う切手に悩んでいるという方は、ぜひ参考にしてください。
結婚式招待状に貼る切手の基本

まずは、結婚式の招待状に貼る切手の基本から見ていきましょう。
結婚式の招待状を郵送するにあたって、切手は必要不可欠。
切手は、招待状を送る際の封筒に貼る用と、返信はがきに貼る用の2種類を用意します。
返信はがきには、切手をあらかじめ貼っておき、招待状に同封しましょう。
切手の金額は、招待状の重さによって異なります。
では、重さ別の切手の料金について、詳しく見ていきましょう。
切手の料金
結婚式の招待状は「定形郵便物」にあたるので、基本的には110円切手を貼ればOK。
しかし、重さが50gを超える場合や、特殊な形の封筒を使う場合は「定形外郵便物」となり、140円以上の切手を貼る必要があります。
このあと詳しく紹介しますが、結婚式の招待状によく使われる「慶事用切手」には、85円と110円の2種類しかありません。
重さが50gを超える場合や、特殊な形の封筒を使う場合は、慶事用切手1枚では送れなくなってしまうので、注意が必要です。
返信はがきには、85円切手を貼ります。
結婚式招待状に貼る「慶事用切手」の選び方

結婚式の招待状には「慶事用切手」を貼るのが一般的です。
慶事用切手とは、お祝い事を知らせる手紙や招待状に貼るための切手のこと。
通常の切手とは異なり、おめでたい柄や吉祥文様が描かれているのが特徴です。
現在発売されている慶事用切手は、85円と110円の2種類。
85円のほうには鶴の絵が、110円のほうには蝶の絵がデザインされています。
どちらも赤やピンク、金色が使われた華やかなデザインになっており、結婚式のようなお祝いごとにぴったり。
結婚式の招待状においては、返信はがきに85円の慶事用切手を貼り、招待状の封筒に110円の慶事用切手を貼るようにしましょう。
慶事用切手を使わない送り方もありますが、目上の方への招待状や親族への招待状には、慶事用切手を使うのが一般的。
まとまった数の慶事用切手を購入したい場合は、事前に郵便局に確認するのがおすすめです。
おしゃれなグリーティング切手もおすすめ
おしゃれな切手を使いたいという方には「グリーティング切手」がおすすめです。
グリーティング切手とは、さまざまな行事やお祝い等のあいさつ状に利用できるように作られた、デザイン性の高い切手のこと。
先ほど紹介した慶事用切手が和風のデザインなのに対し、グリーティング切手は洋風のデザインが多数販売されています。
グリーティング切手は、水付け不要のシール式であることも特徴のひとつ。
面倒な水付け作業がいらないので、新郎新婦の手間を削減できます。
グリーティング切手は、季節ごとに発行されるデザインのほかにも、趣向を凝らしたさまざまなデザインのものが発売されています。
どのデザインもシール式になっているため、貼りやすく、招待客が多い場合にも重宝するでしょう。
結婚式招待状に貼る「オリジナル切手」の作成手順

郵便局では、お気に入りの写真やオリジナルのイラストを切手にできる「オリジナル切手作成サービス」が提供されています。
このサービスを使うと、世界にひとつだけのオリジナル切手を作ることが可能。
結婚式の招待状の場合は、前撮り写真などを使用することで、おしゃれで素敵な切手を作ることができます。
オリジナル切手の作成手順は、以下の通りです。
- オリジナル切手の作成手順
-
- 切手にしたい写真やイラストを用意する
- 画像ファイルをアップロードする
- フレームを選択する
- レイアウトを調整する
- 仕上がりイメージを確認して、完成
オリジナル切手を作成してから手元に届くまでには、注文から約3週間かかります。
結婚式の招待状に使いたい場合は、なるべく早いタイミングで、余裕をもって注文するようにしましょう。
オリジナル切手は、シール式の110円郵便切手×30枚で、1シート3,720円で作成可能。
85円郵便切手×30枚は、1シート2,970円で作成でき、それぞれ切手シート代金のほかに送料が別途かかります。
納期や料金も考慮した上で、オリジナル切手作成サービスを利用するかどうかを決めましょう。
結婚式招待状の料金別納とは?

結婚式の招待状を10通以上郵送する場合は「料金別納郵便」を利用するという方法もあります。
料金別納郵便とは、切手を貼る代わりに、郵便料金をまとめて支払うことができるサービスのこと。
たくさんの郵便物を一気に送りたいというときに、切手を貼る手間をなくしたものが、料金別納郵便です。
料金別納郵便を利用したいときは、封筒の切手を貼る場所に「料金別納郵便」と表示するのが決まり。
この表示は、切手の代わりに料金別納スタンプを押してもらうのですが、こだわりたいカップルはオリジナルでデザインすることも可能です。
料金別納郵便の表示は、印刷するほかにも、既定のサイズ内であればオリジナルのスタンプやシールを作って貼ってもOK。
デザインによっては使用できないこともあるようなので、事前に郵便局へデザインを持ち込んで、確認してもらうと安心ですね。
料金別納郵便は、招待状の切手部分までこだわりたいという、おしゃれカップルに人気。
料金別納郵便にしたい場合は、切手を買わずに、郵便局の窓口で送料を払って手続きします。
結婚式招待状で失敗しない!重さチェックと切手の貼り方

結婚式の招待状を送るときに気を付けたいポイントは、以下の通りです。
- 結婚式の招待状を送るときの注意点
-
- 実際に封入して重さを確認しておく
- 招待状1通につき切手1枚が基本
- 横書きは「右上」縦書きは「左上」に切手を貼る
- 手渡しの場合切手は不要
では、結婚式の招待状を送るときに気を付けたいポイントについて、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
実際に封入して重さを確認しておく
切手の金額は、招待状の重さによって変わります。
基本的には110円で送れますが、重さが50gを超える場合は140円以上分の切手が必要。
切手を貼り終えていざ送ろうとしたときに「切手の料金が違った」ということが起きないように、必ず実際に封入して重さを確認しておくようにしましょう。
招待状1通につき切手1枚が基本
切手は、招待状1通につき1枚が基本。
複数貼りはなるべく避けるようにしましょう。
重さが50gを超える場合や、特殊な形の封筒を使う場合は「定形外郵便物」となってしまい、140円以上分の切手を貼る必要があります。
慶事用切手は85円と110円の2種類なので、定形外郵便物になってしまうと、慶事用切手1枚で送ることができません。
この場合は、金額の大きい普通切手を使うのがおすすめです。
横書きは「右上」縦書きは「左上」に切手を貼る
切手を貼る位置は、封筒の文字が横書きか縦書きかによって異なります。
横書きの場合は、右上に貼るのがルール。
縦書きの場合は、左上に貼るのがルールです。
返信はがきの場合も同様に、横書きは右上、縦書きは左上に切手を貼りましょう。
手渡しの場合切手は不要
招待状を手渡しする場合は、封筒に切手を貼る必要はありません。
しかし、手渡しの場合でも返信はがきには切手を貼る必要があります。
招待状が手渡しの場合は、返信はがきも手渡ししてもらえる可能性も高いですが「郵送と手渡し、どちらでも良いですよ」という意味を込めて切手を貼るのがマナーです。
まとめ

今回は、結婚式の招待状に必要な、切手の選び方や貼り方を解説しました。
結婚式の招待状は、基本を押さえつつ、おふたりらしさのある切手を貼って送りましょう。
「結婚式の招待状に貼る切手について悩んでいる。」
「招待状の切手の貼り方が知りたい。」
という方は、この記事を参考にしてくださいね。
「素敵な結婚式になりますように。」
ブラプラはそんな気持ちでおふたりを応援しています!

ブラプラ編集部
ブラプラはあなただけのオリジナルウェディングができる初めてのWEBサービスです!コラムやSNSではウェディングの不安や疑問を解消できるような情報を発信中!